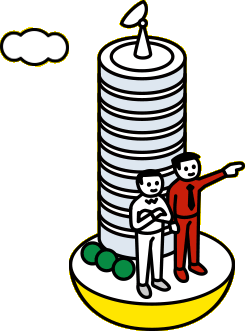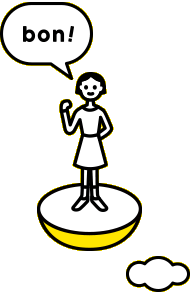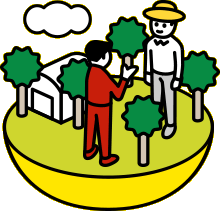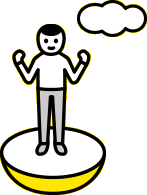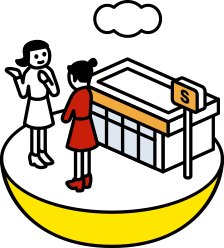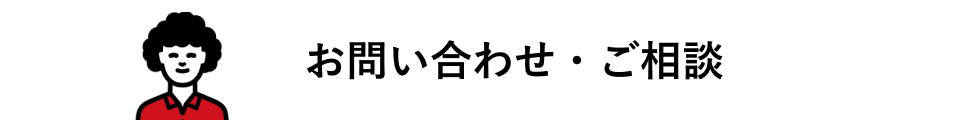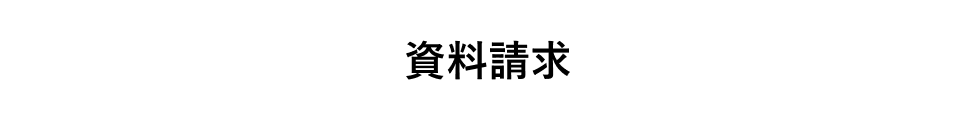SEOとAEO/LLMO/AIOは全く違う。bonが考える“AI時代の最適化”の本質とは
「SEOとAEOは似ている?」
最近、「SEOとAEOって、結局は同じことでは?」という声を耳にします。
確かにどちらも“最適化”という言葉がつきますし、
「誰のために発信するのか」「どんな課題を解決したいのか」といった根本の考え方は共通しています。
けれど、私たちbonはSEOとAEOは別物であり、あまり安易に「同じだ」と着地するのは違うと考えています。
SEOが“検索エンジンのための最適化”であるのに対し、
AEO(Answer Engine Optimization)は“AIが人に答えを届けるための最適化”です。
つまり、人に届くまでのプロセスがまったく違う。
その結果として、考えるべきことも、やるべきことも、大きく変わってきています。
AEO時代に押さえておくべきポイントは、大きく2つあります。
1つ目は「オウンドメディアだけでなく、PESO全体を最適化すること」。
そして2つ目は、「自社ブランドを明確にすること」です。
※ここではLLMO、AIOなどを便宜上、AEOに統一します
目次
オウンドメディアだけではなく、PESO全体を最適化する
かつてのSEO:O(オウンドメディア)だけを磨けばよかった
従来のSEOでは、「検索で見つけてもらうこと」がゴールでした。
そのため、記事の量と質を担保できればアクセスは自然と集まり、
SNSや広告などは“別の領域”として扱われてきました。
この構造の中では、コンテンツ制作に十分なリソースを持つ企業ほど有利であり、
“資金力のある会社が上位を取る”という時代でもありました。
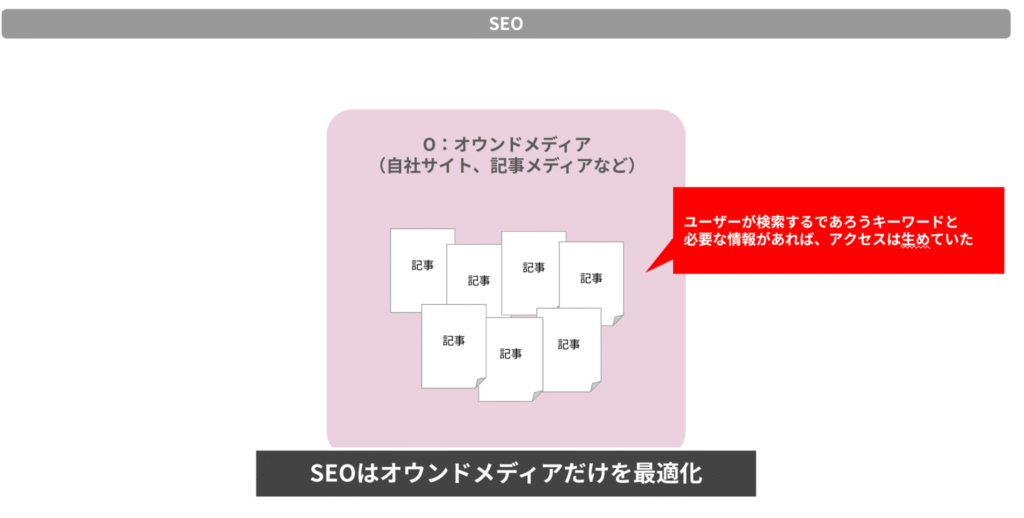
実際にbonでも過去、お客さまの記事メディアを運営させていただき、
1年目で170万PVを達成した実績もありますが、特に広告やプレスリリースなどは打ったことは無かったので、実質オウンドメディアだけで評価されていたと思います。
ちなみにそのサイトは弊社の手から離れていますが、やはりAIの影響でアクセスが減少している用です。
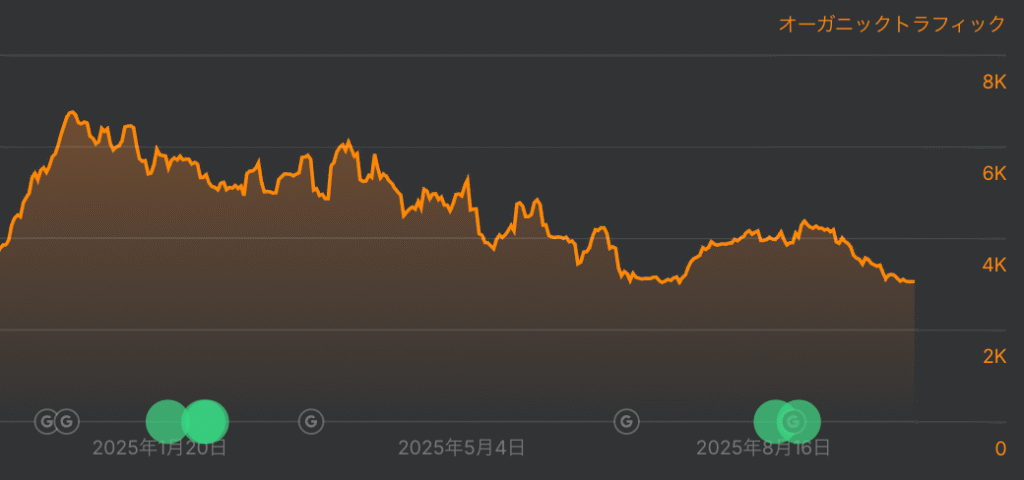
AEOの登場:AIが“全体像”を見て判断する時代に
しかしAEOの登場により、この構図は大きく変わりました。
AEOとは「AIに理解され、信頼され、引用されるための最適化」。
AIは、単に記事の中身を見るだけではありません。
その企業がどんな発信をしているか、どんな評価を受けているか、
ユーザーとの関係性はどうか──
つまり、“PESO全体”の整合性と信頼性を見ています。
ここでいうPESOとは、
- P(Paid Media):広告・リスティングなどの有料メディア
- E(Earned Media):ニュースリリースや取材記事などの第三者メディア
- S(Shared Media):SNSや口コミなどの共有メディア
- O(Owned Media):自社サイトや記事メディアなどの自社資産
の頭文字を取った考え方です。
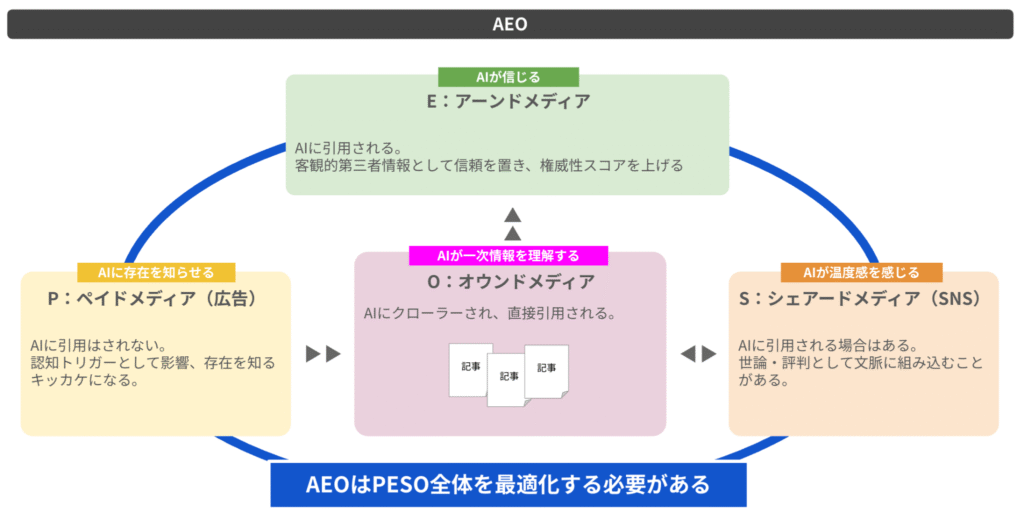
AIは、これらすべてを横断的に読み取り、
「この企業は信頼できるか」「どんな文脈で話題になっているか」までを判断します。
bonが提案する“PESO連動型”の最適化
bonでは、この変化を踏まえ、オウンドメディア単体ではなく、
PESO全体を一つの“信頼構造”として設計することを重視しています。
- P(広告):AIに“存在を知らせる”認知トリガーとして活用
- E(第三者メディア):AIが“信じる情報源”としての外部評価を確保
- S(SNS):人の感情や共感を可視化し、“温度感”を伝える場として活用
- O(自社サイト):AIが直接クロールし、一次情報を理解する中心点
これらを一貫して最適化することで、
AIにも人にも信頼されるブランド構造が生まれます。
ただし、少しだけ注意してほしいのが、オウンドメディアとアーンドメディアはよくAIが閲覧しているのですが、P(広告)はほぼ引用されないこと、S(SNS)の閲覧は多くなさそう、ということはご留意いただいても良さそうです。
- P(広告):内容を引用することは無い
- E(第三者メディア):内容を引用するし、信頼の評価になる
- S(SNS):あまり見てなさそう…
- O(自社サイト):一次情報を理解する中心
自社ブランドを明確にする
「誰が発信しているか」をAIは見ている
AEOの時代においては、“何を伝えるか”と同じくらい、“誰が伝えているか”が問われます。
たとえば──
うどん屋さんが書いた「うどんの記事」と、
ラーメン屋さんが書いた「うどんの記事」。
どちらを信頼したいかと聞かれれば、多くの人が前者を選ぶはずです。
これは人の感覚だけでなく、AIも同じです。
AIはコンテンツの内容だけでなく、「どんな企業が、どんな立場で発信しているか」を見た上で、「ユーザーにこの情報を届けて良いか」を判断しています。
私もよくありました。
GA4の解析について調べたところ、一番上にあった記事を開くと印刷屋さんの記事。
印刷屋さんを否定するわけではまったく無いのですが、正直に申し上げると「印刷屋さんがGA4を深く理解しているとは思えない」が正直な感想であり、やはり記事も私が求めるものではありませんでした。
つまり、AEOでは企業のドメインや理念などをトータルで表すブランドそのものが信頼の基準になります。
AIは“ブランドの文脈”を理解しようとしている
AIが回答をつくるとき、単に記事を引用しているわけではありません。
前述した通り、企業の公式サイトやニュース記事、SNSの反応などを横断的に分析し、
「この会社はどんな領域で語られる存在か」「どんな価値を持っているのか」を判断しています。
言い換えると、AIは“そのブランドの文脈”を理解しようとしているのです。
そして、この文脈の中心にあるのが、CEP(Category Entry Point)=カテゴリーエントリーポイントです。
bonが考える「CEPを軸にしたAEO設計」
CEPとは、ユーザーがある商品やサービスを思い出す“きっかけ”になる言葉や状況のことです。
たとえば「寒い日にはあのコーヒー」「人事制度の見直しならこの会社」といった、想起の入口(エントリーポイント)。
AIも同様に、文脈やシーンの中で「この領域ならこの会社」と紐づけて理解します。
※これはAIの中長期の理解となり、また別記事でご紹介いたします。
そのため、AEO時代のブランドづくりでは、
このCEPを意識的に設計し、自社がどんな領域の“代表回答”として認識されたいかを明確にすることが重要です。
たとえばbonであれば、
「ブランディング ✕ 制作」「中小〜中堅企業のデジタル施策」「AI時代のWeb戦略」などのカテゴリーで、
“信頼できるパートナー”としてAIやユーザーに想起されることを目指しています。
このようにCEPを定義することで、
- サイトの記事構成やトピック(O)
- プレスリリースや記事露出(E)
- SNSでの発信テーマ(S)
- 広告メッセージ(P)
といったPESO全体が“同じ文脈”で統一され、AIからも一貫性あるブランドとして評価されるようになります。
※CEPの策定には、市場のインパクトや、そもそも自社がそれに相応しいか、競合の手抜かりを突けるのか、など複合的に考える必要があるため、こちらも詳細は別記事に譲ります。
AEOは「信頼の構造化」から「想起の設計」へ
SEOが「知見を書けば届く」時代だったとすれば、
AEOは「信頼され、思い出してもらわなければ届かない」時代です。
SEOの知見は、今も発信基盤として欠かせません。
しかしAEOでは、単に記事を量産するのではなく、
AIが“どんなカテゴリーであなたを思い出すか”を設計することが鍵になります。
AIは、「このテーマならこの企業」と判断できる“理由”を探しています。
その理由づくりこそが、PESO最適化とCEP設計の役割です。
bonは、AEOを“技術”ではなく“信頼と想起のデザイン”と捉えています。
AIにも人にも「この領域ならbon」と想起される存在であること。
そのために、戦略からブランド、コンテンツまでを一貫して設計し、
クライアントの「選ばれる理由」を共につくっていきます。